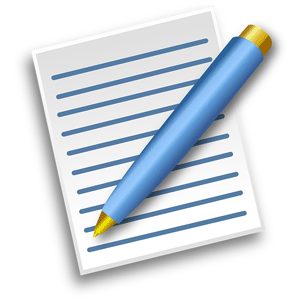「君影草」 音更町 T・H
札幌冬期オリンピックのあった翌年の昭和48年7月22日、私達に待望の女の子が誕生した。「うちの子が一番美人だな」などと、夫と一緒に嬉しさのあまりに食事をとるのも忘れ、病院の保育所のガラス越しに、ちいちゃな寝顔をいつまでも見つめていたものだ。この子の名前は、「佳子」です。
突然の悲報は、平成3年2月27日であった。朝、元気に「行って来ます」と言ういつも通りの声を残して。
午後6時半ころ、音更消防署から「佳子さんが交通事故に遭い、帯広協会病院のほうに搬送されました」との連絡に、私は受話器を握りしめたままその場に座り込んでしまった。早速、病院に向かい外来の診察が終わった病棟、シーンと静まりかえった廊下に1人立ち、重々しい時間が私を襲う。やがて病院に来た警察官から、佳子はバス停から自宅に向かう途中、横断歩道で乗用車に跳ねられたことが判った。
ストレッチャーに乗せられた娘の顔は真っ青、そして「青で渡っていたのに・・・」と悔しそうな顔をして佳子は答えた。その後容体が急変し、午前11時32分、医師はついに佳子の臨終を告げた。死因は「脳挫傷」だった。くしくもひな祭りの3月3日に通夜が行われたが、私は佳子の死が悪夢を見ているように思えてならなかった。
黒いリボンがかけられた遺影から、今にも「お母さん」という声が聞こえてくるような気がしてならなかった。
葬儀の後始末を終えた主人が単身の勤務先に戻る時、「もう、頑張る事が出来ない・・」と言いながらも、仕事への義務感、一家の大黒柱としての責任感を背負って、再び任地に向かう主人の思いは、おそらく複雑なものだったに違いない。
そして、自宅には私と佳子のお骨が残った。わずか17歳の命だった。
遺影を前に悔恨の思いにさいなまれる日々が始まった。
加害者の自分の方の信号は青だったと思うと言う言葉は、目撃者の証言で一変「赤だったかもしれない」と自分の過失を全面的に認めた。加害者への判決は、「懲役1年6ヶ月、執行猶予3年」だった。なんということだ。一方的に法を犯して人間ひとりの命を奪いながら執行猶予とは。これでは、17歳で命を奪われた佳子があまりにも不憫すぎる。目撃者の方や友人、知人への感謝の反面、報われない沈痛な思いは、生涯消えることはないと、その時感じた。
事故の防止には、刑事、民事、行政の3つの責任の抑止力が作用し合うことが必要だが、被害者の立場から見れば、いずれもが不十分である。警察の捜査状況はもちろん、起訴・不起訴の決定さえしらされない。公判日程の連絡もない。
すでに、佳子が突然いなくなって6年近くの月日が流れたのに、私には時間が止まったままの気がしています。罪もない、希望を持った17歳の娘の命を奪った交通事故、佳子にもそして私達残された家族にとっても、あまりにも残酷すぎる仕打ちです。いつも私の耳元には、「お母さん、お母さん、佳子は17歳でなんか死にたくなかった」という声が聞こえて離れません。
事故防止を訴える活動は辛く、容易な事ではありませんが、住子のような犠牲者を決して出してはいけない。
私のような苦しみは誰にもさせてはいけない。